はい桐沢です!
前回「リズムにハマったまま練習をする」というブログを書きました!これがかなり好評でしたので少し深堀します。
前回のテーマは「リズムにハマっているか分からないまま練習を続けるのは危険」
リズム感は文字の如くアナログな人間の力ですが、僕らはそこを理解する為の道具はデジタルしか持ち合わせていません。
そこに僕らがリズム感に悩むギャップがある事は間違いなさそうです。
リズム練習の問題点
僕の経験上、日本人は世界でもっとも練習熱心である民族である事は間違いなさそうです。
しかしなぜそんな練習熱心な僕らは世界に向かって「リズム感が良いんです!」といつまで経っても言えないのか?
皆さんも知っているように「リズム感を向上させたかったらメトロノームを使え!」
結局僕らはメトロノームというデジタルで練習しても実際の演奏でメトロノームを使う事はあまりありません。
最後は自分の『リズム感を信じる』というまあなんとも「精神論」とも言えるアナログな物を頼りにしなくてはいけません。
しかし選択肢はデジタルしか持ち合わせていない、、。
ならばそのアナログにフォーカスした練習方法を組み上げる事が非常に重要。
今回はどうやったらアナログであるはずの「リズムにハマったまま練習をする」が出来るのかを皆さんと考えていきたいと思います。
同じ事をしない
僕は練習をかなりルーティン化しているという動画を出しました。
内容は毎回同じ練習をするのですが『やり方や切り込み方をたくさん持つ』というものです。
ドラムの話で申し訳ないのですが(なんで?)僕は同じ教則本の同じページを深堀するのが大好きなんです。
どういう事かというと、教則本に書いてある事が出来たらそれをガイドにし、自分の持っているリズムと照らし合わせる作業をしています。
言葉だけだと分かりにくいのですが、例えばこんな譜面

恐ろしく簡単ですね、ドラマーでなくても簡単に出来ます。
これが出来たとしても僕は次のページに進むのではなく、このフレーズから自分のリズム感を多角的に探ります。
練習のアイデア
この簡単な練習は簡単だからこそ深堀でき自分の中身と向き合えます。
キーワードは「自分のリズム感と照らし合わせる」
練習の展開アイデアとしては
メトロノームを使う時
メトロノームを使わない時
この違いを僕らのアナログの感覚はどんな反応や判断をするのか?
ここに何か情報はあるはずです。
「メトロノームがないと不安」というのも立派なアナログの感覚の反応です。
ここから
なぜ不安を感じるのか?
どうしたら不安を感じなくなるのか?
と禅問答のような深堀ができます。
他のアイデアとしては
足踏みをする
足踏みをしない
この違いはなんなのか?にフォーカスをしてみる。
これをすれば、
なぜ演奏中に足踏みをする人が多いのか?
その足踏みの精度ってどうなのか?
その足踏みの精度を上げるにはどうすれば良いのか?
など思考する事ができます。
同じ事を練習していますが自分の感覚を多角的に検証するため、自分の中の変化に気づきやすくなります。
「同じ事を繰り返さないルーティーン」とはやり方の種類をたくさん持つという事です。その中から僕は様々なアイデアを見つけ、身体とリズムの関係を深めていきました。
このバリエーションはまだまだありますが、この数字というデジタルに頼らないアナログなリズムへの向き合い方を皆さんご自身で探ってください。
デジタルからアナログへ

「身体のここが何か動く感じ」など僕らのアナログな感性が発信する微弱なメッセージを信じる価値は大きくあり、ここにデジタルで組み上げるリズム感からアナログなリズム感に移行するヒントは絶対にあります!
「同じ事を繰り返さないルーティン練習」の目的は、自分の中のリズム感の変化に気づきやすいという事になります。
アナログの繋がり
僕が最近どハマりしているグループを紹介したいと思います。
この動画は僕が2020年で見たリズムのパフォーマンスでは堂々1位になりそうです。
このパフォーマスは口琴以外は全て人間の身体で音を出しています。
かなり複雑なリズムを刻んでいますが、一糸乱れません。
しかも誰もリズムと格闘していないんです。
僕らの数字で出来上がったリズムとは全く違うリズムの世界。
ここから僕らが「リズムに苦しむ理由は数字」との仮説も簡単に立てる事ができます。
この「Barbatuques」はブラジルのグループでポルトガル語名です。いまだに僕は読み方がわかりません。彼らの動画も英語の字幕で見ています。
リズムのオンライコミュニティーに参加していただいている
「隊長」三浦 晃嗣さん曰く
「あえてカタカナで書くなら“バルバトゥーキス”」だそうです。
おそらく発音はもっとポルトギー(ポルトガル語)だと思います。
関連動画から彼ら彼女らを探っていくと、リズムを全て身体で表現するというアナログな力に圧倒されるので、皆さんに是非ハマってください。
生み出される振動
身体を叩く事で「振動」が生まれます。それは世界一リズム感の良い耳の聞こえないエヴィリン・グレニーの世界です。
そんなブログを書いています
『リズムのチューニング』
振動を知るとリズムと身体の関係を知る事ができ、僕らの知らないリズムの世界の入り口に連れて行ってもらえます。
リズムはアナログ

先ほども書きましたが、結局僕らはメトロノームというデジタルで練習しても実際の演奏でデジタルなリズムを使う事はあまりありません。
最後は自分のリズム感を信じるという「精神論」とも言えるアナログな物を頼りにしなくてはいけません。
ならばそのアナログにフォーカスした音楽への取り組みを始めて見ませんか?
アナログな方が人間の力が必要です。
だから人を感動させられる
今日のLAからはこんな感じです!
皆様良い1日を 桐沢でした!


 先ほども書きましたが、結局僕らはメトロノームというデジタルで練習しても実際の演奏でデジタルなリズムを使う事はあまりありません。
先ほども書きましたが、結局僕らはメトロノームというデジタルで練習しても実際の演奏でデジタルなリズムを使う事はあまりありません。



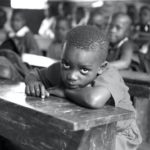
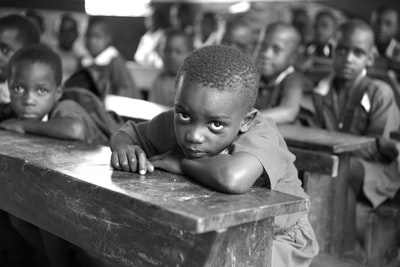




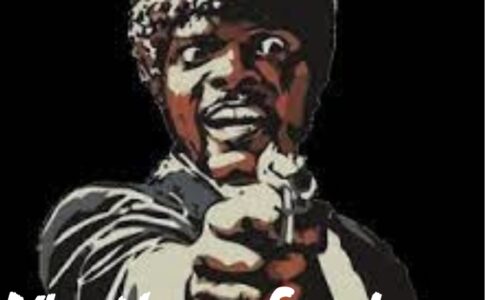

コメントを残す