はい桐沢です!
最近ハマりにハマりまくっているブラジルのボディパーカッション軍団
『barbatuques』

本当に素晴らしい人間のアンサンブルを見せてくれます。
リズムオタクの僕にとっては、ここにこそリズムの最大限の使い方があり、僕らの知っているリズムの姿とは何かが大きく違う。
そんなことをビシビシ感じます。
音楽? 遊び?
言葉で説明するよりも彼らの動画を見ていただきたいのですが、
まずこれは
音楽なのか?遊びなのか?はたまたスポーツなのか?
なんともカテゴライズできない物ですが、リズムを使っている事は間違いなさそうです。
リズムを数えているのか?
動画ではリズムの中で音をピンポン球のように飛ばし、素晴らしいパフォーマンスを見せてくれます。
注目していただきたいのは、そのリズムの組み合わせの最中、誰もカウントを1234と数えていない。
なのに16分音符の裏とかにバシバシ音が入ってきます。
僕らはこれを1234と数えタイミングを狙いますが、彼らからはそれが見えません。
一番最初にピンポン球と表現したのはここからで、音を玉に置き換えるという遊び(卓球)にするとカウントを1234としなくても16分音符の2個目とか4つ目に音を打ち返せます。
ただ飛んできた音をラケットで打ち返す。という遊びにも見えます。
子供のあそび
このリズムを使った遊び、ブラジルの子供番組でも見つけることができます。
番組内では身体を叩いて、歌って、踊る まさに子供が喜ぶ内容
これは中南米のスラングで「タンバレイヨ」呼ばれるもので
叩きたかったら歌え歌いたかったら踊れ踊りたかったら叩け
叩く歌う踊るは同じことで切り離してはいけない。
それが子供番組にもしっかり入っています。
日本のリズム遊び
先程のブラジルの子供番組を見て、
「やっぱブラジル人は子供の頃からリズムを使った遊びをしているからリズム感がいいんだ」
と感じる方もいると思いますが、ところがどっこい我々日本人も子供の時はリズム遊びをしていました。
こんな遊びをやった記憶はありませんか? 身体を使ったリズム遊びで、歌までついています。
これはよくみるとかなり複雑な手の組み合わせとリズムです。
もしかしたら僕らのような教育を受けてしまったミュージシャンは譜面に起こし分析しないと今となってはこの「アルプス一万尺」は出来ないのではないでしょうか?(笑)
リズムに悩み始める
 僕らは子供の頃このようなリズムを使った遊びをたくさんしました。
僕らは子供の頃このようなリズムを使った遊びをたくさんしました。それはブラジルでも日本でも同じだと思います。
しかし大きな違いは、僕らにはその子供の時に遊んだリズムと今のミュージシャンが使うリズムに共通点がないのです。
教育の中で音楽を始める時に数字で表したリズムを習い、それまでの遊びで培ったリズムとは関係性を絶たれます。
僕らは子供の頃にリズムで遊びながら、
テンポが早くなったとか、遅くなった
と悩みながら遊んだ記憶は一切ありません。
一番最初に紹介したbarbatuquesの素晴らしいリズムのアンサンブルはブラジルの子供遊びの延長線上にあるからこそ、誰もリズムに苦しんでいないとも言えそうです。
僕らも子供の時に遊んだ「リズム」と後から習得したミュージシャンの「リズム」この絶たれてしまった関係性に注目するべき価値はありそうです。
こちらの記事でブラジルの子供番組のリズムと、barbatuquesのリズムのつながりを詳しく解説しています。
「リズム感がいい人はなぜリズム感がいいのだろう」
LAからはこんな感じです。
みなさん良い1日を! 桐沢でした!







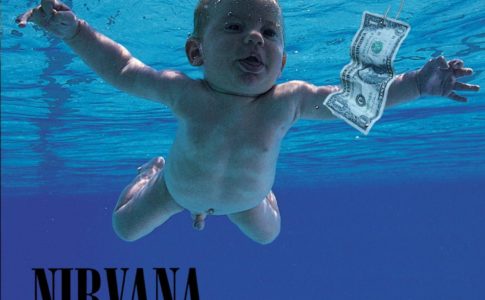





コメントを残す