はい桐沢です!
最近いろいろな所で僕がハマっていると言っている物が、
ブラジルの子供番組
大の大人が子供番組にハマるなんて、なんともキテレツですが様々な発見があります。
番組の中では子供たちはテンポが走る 遅くなるとか悩む前にリズムにハマることを身体を叩いて知る。
これを「リズム感の第1のスタートポイント」としましょう。
これはリズムオタクの僕からすると、ここにはリズム感に関する全てが詰まっています。
知識や練習ではない、遊びの中で育まれるリズム。
そんな事がブラジルの子供番組からは見えます。
日本の遊び

もちろん僕らにもこの「遊びの中で育まれるリズム」に子供の時に囲まれていました。
ケンケンぱセッセセーのよいよいよいアルプス一万尺じゃんけんぽい、あっち向いてホイ
これらには全てリズムがあります。
アフリカンコンセプトを知っている方なら、これらの日本の遊び歌の中にもアフリカンコンセプトを感じる事ができます。
アフリカンコンセプトって? 方はぜひこちらを
リズムを習う
 僕らは音楽を学ぶと同時に、初めてリズムを数字でヴィジュアル化した譜面というものに出逢います。
僕らは音楽を学ぶと同時に、初めてリズムを数字でヴィジュアル化した譜面というものに出逢います。
これは遊びの中で育まれる「リズム感の第1のスタートポイント」との関係性は一才関係のない全く別なものとして数字でリズムを1から学びます。
ブラジルではこの遊びの中で育まれるリズムが、そのまま今の音楽のリズムにつながっています
詳しくは僕のこちらのブログを読んでいただきたいのですが
子供の時の身体を叩く動作、近所の子供たちの遊びと今の音楽が一直線で繋がっているのが見えます。
アフリカの子供達
国を変えてアフリカ・ザンビアでの話
ザンビアは元イギリスの植民地のため、イギリスの宣教師がザンビアの子供たちに「近代化するための教育」という目的で西洋式で「きらきら星」を教えています。
残念ながらその子供達の歌声はぐちゃぐちゃです。
イギリスからの宣教師はもちろん善意で西洋式の歌い方をザンビアの子供達に教えています。
しかしそれは子供達が「遊びの中で育んだリズム」とは全くつながりが見えず、西洋式の中では「うまい」とはお世辞でも言えません。
しかし本当のザンビアの子供たちの歌声はこんなにも素晴らしいものです。
僕らの歌声
ザンビアの子供達がイギリスの宣教師に教わった歌声、僕らが子供のころの歌声に似ていませんか?
いかにも子供らしいバラバラな感じ。懐かしいです。
このバラバラ感を矯正するために数字のリズムを教えられます。
この時点で僕らが遊びの中で育んだリズムとは完全に関係性は遮断されます。
ここに何かあまり嬉しい言葉ではないのですが「日本人のリズム感」の成り立ちを感じます。
これが僕らの「リズム感の第2のスタートポイント」で、第1とは全く別な物です。
しかしアフリカ・ザンビアやブラジルでは「リズム感の第1のスタートポイント」の延長線上に今の音楽があり、遊びの中で培ったリズムはそのままつながっています。
この動画は僕が見た2020年ベストパフォーマンスの最上位に入ります。
本当にリズムが素晴らしい
遊びの延長線
ブラジルの子供番組に戻します。
番組の出演者からのメッセージに大きなヒントがあります。
人間の身体は、私たちの最初の楽器と考えてもいいでしょう。私たちは最初から、心拍、呼吸、歩行のようなリズムの存在をその中に持っています。
「人間の身体は私たちの最初の楽器」 いい言葉ですね!
番組に出てくる子供たちは、おそらくですがまだ楽器を持っていません。
ということは楽器を持つ前にリズムで遊びます。
まあ僕らもそうでしたね!
楽器を持つ前にリズムを使って遊ぶ「リズム感の第1のスタートポイント」
このプロセスと僕らの受けてきた「リズム感の第2のスタートポイント」
楽器を持ってからリズムを数字で学ぶ
どちらが人間本来のリズム感を育むかは一目瞭然です。
数字でギャップを埋める
このギャップを僕らは後から数字のリズムやメトロノームで穴埋めをしようとします。
なぜならば教育の中でリズム感は「遊びの中とは全く違う、練習しなくてはいけない物」に変わりこれ以外の選択肢があるなんて考えもしません。
これが僕らが受けてきた教育の結果で、けして日本人がリズム感が悪いのではなく、教育の結果、人間本来のリズム感との接点がないまま楽器を演奏を始め今に至ってしまった。
僕らには「遊びの中で育んだリズム」との関係性を探るというアイデアはなく、数字でリズムを解析するしか選択肢がないのです。
しかし僕らはなんとなく「リズム感は数字ではない」とわかっています。
しかしそれを解き明かす選択肢が数字しかない
これこそが今の「日本人のリズム感」を作った元と言えそうです。
ここを見直す価値は十分にありそうです!
LAからはこんな感じです!
みなさん良い1日をお過ごし下さい
桐沢でした。

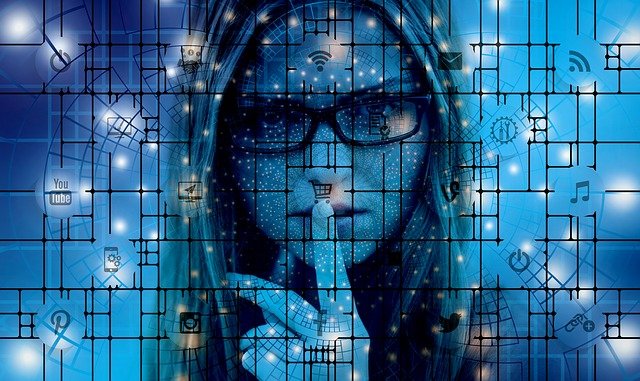











コメントを残す